- 阪神百貨店で阪神タイガース優勝記念グッズ販売始まる 待ちわびたファンらが開店前から長蛇の列
- 防衛費“大幅増額” 過去最大114兆3812億円の来年度予算案、閣議決定 「さらなる増税」の声も|TBS NEWS DIG
- 住宅全焼 焼け跡から身元不明の2遺体 岩手・洋野町(2023年5月18日)
- ロシア軍、侵攻の現実味…プーチン大統領が仕掛ける”危機”【2月9日(水)#報道1930】
- サルだけどリス似!?「ボリビアリスザル」 和歌山「和歌山城公園動物園」 #shorts #読売テレビニュース #すまたん #あにまるウォッチ #動物
- 【5月12日の出来事】発生から公表まで6日…「防球ネット」下敷き 校長が謝罪/初の実態調査で“不適切な保育”914件/藤井キャスター広島取材 など (ニュースまとめ)
“犯罪被害者の声”を加害者へ 12月1日から新たな制度スタート 人員不足など課題も(2023年11月29日)
来月1日から、犯罪の被害に遭った被害者の心情を加害者に伝えることができる新しい制度がスタートする。この制度について長年、犯罪被害者の支援に携わった人物に課題点などを聞いた。
■被害者から加害者へ “伝達制度”スタート
近年、日本では刑法犯として検挙された人のうちの再犯者が占める割合「再犯者率」が高い水準を示している。
2021年は48.6%と、検挙された人の約半数が再犯者となった。
こうしたなか、再犯防止推進の一環として新しい制度が始まる。
小泉龍司法務大臣:「12月1日から、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、運用が開始されます」
「被害者等の心情等の聴取・伝達制度」は、犯罪の被害者や被害者の遺族らが自身の心情などを刑務所などで罪を償う加害者に伝える制度だ。
被害者や被害者遺族側から申し出があった場合に、全国の刑務所の刑務官や少年院の法務教官が「被害者担当官」となり、原則「対面」でその心情を聞き取る。
そして、刑務所や少年院に入所している加害者にその内容を伝えるとともに、施設でもその被害者心情を踏まえた指導や教育を行うというものだ。
さらに被害者側が希望すれば、心情を伝達された際の加害者の反応も知ることができるという。
1日からの制度開始を前に、全国の刑務所など刑事施設の担当職員らは、被害者遺族の講演や、被害者の声を聞き取るロールプレイング形式の「研修」を度々行っている。
■新制度に遺族は…「今までなかった大きな制度」
番組は今回、この新制度について、自らも26年前にひき逃げで息子を失い、それをきっかけに犯罪被害者の支援に携わってきた人物に話を聞いた。
被害者支援団体代表 片山徒有さん(67):「今までなかったとても大きな制度だと思います」
片山さんは、1997年に当時8歳だった息子・隼君をダンプカーによるひき逃げで亡くした被害者遺族だ。
事件以降、犯罪などの被害者を支援する団体の代表を務め、その経験から加害者の家族や受刑者の支援にもあたっている。
来月1日から開始される被害者等の心情等の聴取・伝達制度について片山さんは次のように話した。
片山さん:「まず被害者側が求めるものなんですが、私が出会ってきた被害者のご遺族の方が皆さん口をそろえておっしゃるのは、『心からの謝罪がほしい』ということ。『本当のことを知りたい』ということ」
この制度では、被害者側は自身の心情を伝えた後、加害者側の反応を知ることができる。謝罪の言葉や、犯行に至った理由などを聞くことができる可能性もあるのだ。
片山さん:「例えば、『どうして被害者が選ばれなければいけなかったのか』みたいなことはあまり法廷で語られることはない。加害者の心の内面に迫るようなことはあまりなかったと思う」
被害者は事件がなぜ起きたのか、加害者はどんな思いで犯行に至ったのかなどの疑問にとらわれ、事件から立ち直ることが難しくなってしまうという。
片山さん自身も、加害者がどんな思いで罪を償っているのか、ずっと考えてしまっていたという。
片山さん:「『ここまで加害者のことを考えなければいけないのか』って、答えが出ない問いかけを常にされているようで、それがつらかったですね。加害者がどういう考え方を持っているかフィードバックがあると思っていますので、それは一つの答えになるんじゃないかなと思っています」
■効果は? 専門家「『内省』につながる」
そして、この制度は加害者側にとっても非常に意味のあることだという。
刑務所や少年鑑別所などで1万人を超える犯罪者を心理分析してきた犯罪心理学が専門の東京未来大学教授・出口保行氏は次のように話す。
出口教授:「今回、自ら起こした事件の被害者からの直接の声を聞くことができるというのは、自らが犯した罪の重さを認知していくうえで非常に大きな意味があります」
そして、被害者の直接の声を聞くことで、加害者は再犯を起こさないための次のステップに進むことができると出口氏は言う。
出口教授:「犯罪者たちというのは、言葉は悪いんですが、反省することに慣れているんです。『すみません、もうしません』と反省はする。これでは『次の事件を起こさない』という決意につながっていかない。何がそこで必要かというと、反省ではなく『内省』。自分の何がいけなかったのかをきちんと原因分析していく。(この制度は)内省というものを非常に深めることにつながっていくだろうなと」
■少ない刑務官で担当…人員不足の懸念も
この制度について今一度確認する。被害者や遺族から心情などの聴取の申し出があると、刑務所や少年院などの矯正施設にいる「被害者担当官」が心情を聞き取る。
そして、被害者などから聞き取った心情は 加害者に伝えられ、被害者などから要望があれば加害者に伝達した日付や内容、加害者の反応を被害者などに知らせるという仕組みになっている。
希望に応じて、伝達の時に加害者が述べたことを伝えることもできるという。
ただ、この制度は課題もあるようだ。
被害者などから聞き取りを行う「被害者担当官」が各刑務所、少年院に男女1名ずつ、合計2名以上はいて、基本的には1人の担当官が被害者などからの聞き取り、加害者への伝達、結果を被害者などに伝達するという作業を行うそうだ。
担当官になるのは、刑務所の場合は日頃、受刑者の監視・監督を行っている刑務官などで、特別にカウンセラーのような資格やスキルがある人物ではないそうで、研修などを受けて指名されるそうだ。
こうした聞き取りの作業について、被害者支援団体の代表・片山さんは「かなり昔の事件の被害者まで、要望を受け付けることになるので、少ない担当官で回すのが相当難しくなるのではないか」と人員不足に対する懸念を示している。
今回の制度の動きをロールプレイング形式で行う研修などに参加した刑務官は、「被害者の思っていることを引き出す、聞き出すという聞く力というのがこれからもっと必要になる。これが一番大変だと思う」と、これまで加害者としか接してこなかった担当官がうまく被害者の心情を引き出せるのかも課題だそうだ。
(「大下容子ワイド!スクランブル」2023年11月29日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
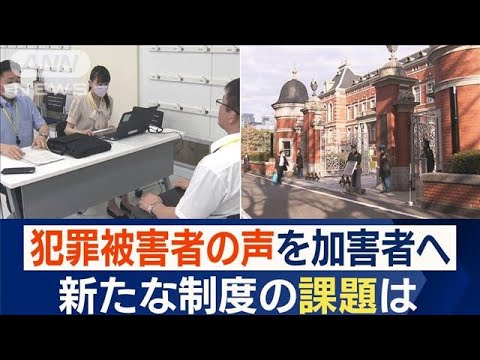

















コメントを書く