【報ステ解説】「物価上昇を超える賃上げは非現実的」なぜ中小企業は難しい?(2023年1月17日)
来週、事実上のスタートを切る春闘。経団連は17日、経営側に求める基本方針を発表しました。
17日に発表されたのが経団連の通称『経労委報告』。これは「春闘における経営側の基本スタンス」が示されたものです。このなかで、賃上げについて、経団連は“企業の社会的責務”として、この報告書を大きな転換点と位置付けています。
◆雇用や労働市場の分析などが専門のニッセイ基礎研究所の斎藤太郎さんに聞きます。
(Q.経営者側の賃上げへの積極的な姿勢を示していて、異例だと思いますが、どう評価しますか)
経営側が率先して賃上げすることは、基本的にはあり得ない姿です。ただ、今回の場合、40年ぶりの物価高で、異常な状態。そのため生活が苦しくなり、社会問題化していますので、経営側も積極的な賃上げの姿勢を示す必要が出てきたと状況だと思います。
(Q.この報告書は、大企業だけでなく、中小企業を含めた姿勢を示すものとみていいのでしょうか)
所属しているのが、ほとんど大企業ですが、今回の報告書では、特に中小企業の賃上げが不可欠だと明記していますので、中小企業にとっても意味のある報告書だと思います。
今年の春闘の賃上げ率について、民間のシンクタンクが「平均で2.85%」との予測を出しました。予測通りであれば26年ぶりの高さとなります。一方、消費者物価指数は、去年11月時点で3.7%の上昇。岸田総理は、年頭の会見で「インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたい」と述べていましたが、物価上昇率を上回る賃上げの実現は難しい情勢となっています。
(Q.この状況をどう見ますか)
まず、数字の確認です。『2.85%』というのは定期昇給を含んだ数字です。労働市場全体の平均賃金を決めるのは“ベースアップ”といわれるところ。そうなると、『2.85%』というのは1%程度です。消費者物価は3.7%ですので、物価と賃金の伸びがかい離している。だから、岸田総理が言うように、今年、これが逆転するというのは非現実的と言わざるを得ないと思います。今年1年で無理です。ただ、これを悲観する必要ではないと思います。物価上昇というのは、ずっと続くものではなく、一時的な要因が大きいので、いずれ落ち着いてくると思います。経済が安定したときに、賃上げ率が物価上昇率を上回るということが重要で、2、3年かかって、それを実現していくことが重要だと思います。
(Q.体力がある大企業は賃上げできても、中小企業は難しいと言われていますが、その点はどうでしょうか)
今回の物価上昇は、原油高、円安といったコスト増が主です。中小企業は、コスト増の影響をより多く受けてしまう。大企業の場合は、価格転嫁がしやすかったり、輸出で円安の恩恵を受けられます。中小企業にはそれがありません。コストが上がった分、価格転嫁が難しい。それが現実だと思います。
(Q.中小企業庁が、去年行った調査でも「すべて価格転嫁できている」としたのが約17%。中小企業の価格転嫁が難しいのであれば、それをスムーズに行うためのカギは何でしょうか)
中小企業の場合、大企業の下請けになっていることが多く、力関係で、価格転嫁がしにくいという構造があります。ただ、今回の報告書で、適正な価格転嫁、取引条件の改善をやっていくように打ち出していますので、そういうことを着実に進めていけば、中小企業も価格転嫁が進んで、収益の改善につながる。そして、賃上げにつながるという好循環を目指していくべきだと思います。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>











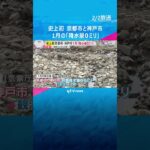






コメントを書く