「感じることが最大の備え」“発生72時間”生き抜くヒントを学ぶ“首都直下”体験ツアーとは?【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG
10万5000人が犠牲になった、関東大震災からきょうで100年です。いつ起こってもおかしくない次の大地震を、リアルな体験を通じて学べる場所があります。大震災発生直後の72時間。支援態勢が十分ではないその72時間をどう生き抜くのか?
■“発生72時間” 必要な備えは・・・
日比麻音子キャスター:
私も「そなエリア東京」に行って実際に体験してきました。ものすごくリアルに作られていて驚きました。現場に行ってみると、校外学習で学校から多くの生徒や、日本語を学んでいる海外からの学生の姿もありました。
取材して感じたのは、まずは「“感じる”ことが最大の備えである」ということです。
参加した子どもに話を聞いてみると「怖かった」という声が聞こえました。実際に停電を経験すると、自分が思っている以上に動揺しました。また家具が倒れている部屋を見てみると「自分の部屋は大丈夫だったかな。ちゃんと動線を確保できていただろうか。やらなきゃ」という危険性を非常に強く感じました。
どうしても想像で「これを備えた方がいいんだろうか」と思っても、なかなか想像が及ばないことがたくさんあるので、とにかく“まずは感じてみる”というのが、大きな備えの一歩になると感じました。
井上貴博キャスター:
防災とか災害は、「少し身構えて難しいことを話し合いましょう」となりがちですが、生活の延長線上で、子どももこういった施設へ行くのは、すごくいいと思いました。
山内あゆキャスター:
体験すると全然違いますよね。
日比キャスター:
そして2つ目の大きなポイントとして「一緒に行って会話のきっかけにする」です。防災の日だからと言って、家族揃って話しましょうとは、なかなかならないですよね。
このような場所に実際に行って体験する。誰かと一緒に行くことで、一緒に危機感や必要性を同じレベルで持つことができ、「どこで会おうか」「どうやって備えていこうか」と自然に会話ができるんですね。
私は1人で取材に行きましたが「家族に連絡を取ろう」と思いました。避難所はどうすればいいだろうとか思いました。パートナーや友人・家族、もし一人暮らしで連絡が取りにくい方も、だからこそ誰に連絡をしようかなど、具体的に想像できるきっかけになると思います。
山内キャスター:
どうやって申し込めばいいんですか。
日比キャスター:
こちら予約が要らないということで、場所に行って、時間を振り分けてもらっていくということで、無料の施設になってます。
井上キャスター:
どのくらいの時間がかかりますか。
日比キャスター:
数十分で回ることができます。2階に行くとこれまでの地震の経験を基に、こういうものが必要だったという、いろんなヒントがあるので、一日中じっくりと見てまわれる施設だと思いました。
いざという時に「どうやって行動すればいいのか」「どうやって情報を集めたらいいのか」というのも、パニックになってしまうと、なかなか判断するのが難しいと思います。TBSにはNEWS DIGというアプリもあります。こういったものを普段から使い慣れておくこともおすすめです。
■どうする? 備蓄品の廃棄問題
地震への取り組み、続いては企業の工夫です。
東京・文京区にある凸版印刷の本社では、一部の奇数階と全ての偶数階に、食料や女性用品などが保管された備蓄倉庫が置かれています。元々は地下に置いていたのですが、過去の震災の経験から、エレベーターが使えなくても大丈夫なように変更しました。
取材すると72時間安心して会社にいられる備え、そして安心して家庭に帰る、帰るまでが防災というのも非常に勉強になりました。
ただ、取材した「凸版印刷」でも備蓄品を、かなり循環をさせてローテーションを組んでいますが「備蓄品の廃棄問題」が見えてきます。この課題に対して、ある取り組みをしている方々がいます。
【ストックベース】
災害備蓄品の廃棄削減をするということで、菊原美里さんと関芳実さんが始めた取り組みです。
大きな企業となると会社にある備蓄品が余ってしまいます。一方で子ども食堂など備蓄品を必要としているところがある。ここをマッチングして、ストックベースが中心となり、余ったものを渡す。このように、必要な分だけ準備ができるシステムがあるということです。改めて「自分の会社は大丈夫かな」と見直すきっかけになりました。
井上キャスター:
備蓄品が特別なものではなく、生活の中の食事の一つなんだというところに、考え方を持っていかないといけないのかなと思います。
山内キャスター:
会社も備蓄品を用意する時に、このあと子ども食堂で再利用しやすく、何かのメニューに使えるものを備蓄すればいいということですよね。だから品物の選び方も変わってきますよね。
井上キャスター:
全てが良いサイクルで回っていけばいいですよね。
▼TBS NEWS DIG 公式サイト https://ift.tt/i9s02Mf
▼チャンネル登録をお願いします!
http://www.youtube.com/channel/UC6AG81pAkf6Lbi_1VC5NmPA?sub_confirmation=1
▼情報提供はこちらから「TBSインサイダーズ」
https://ift.tt/GBTl0Xd
▼映像提供はこちらから「TBSスクープ投稿」
https://ift.tt/Fex9fRv




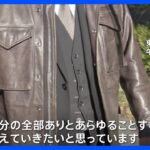
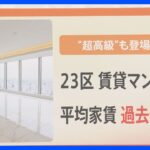
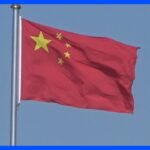





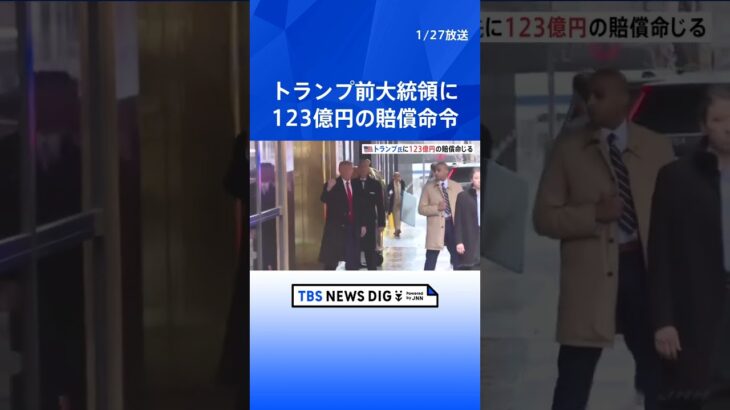
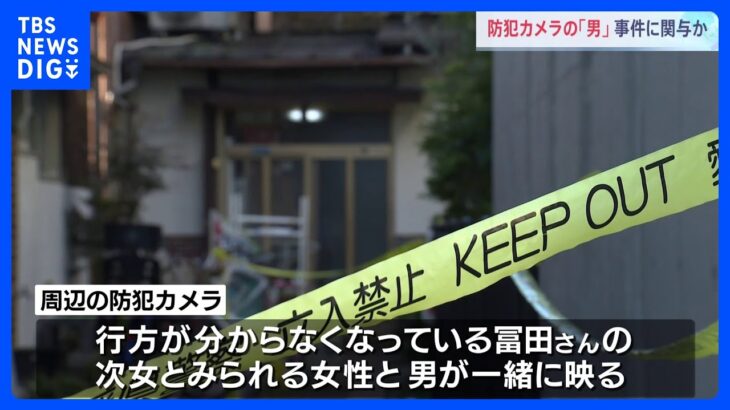


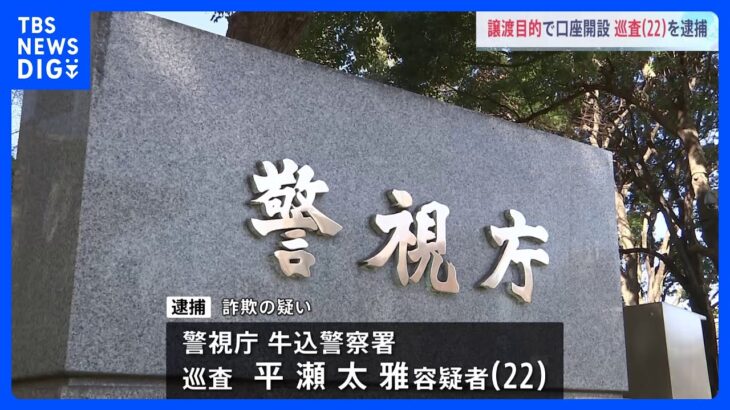

コメントを書く