- 政府、5月8日以降の入国時ゲノム解析と対中国の水際緩和を発表 |TBS NEWS DIG
- 【速報】ゼレンスキー大統領 「戦闘さらに激しくなる」(2022年3月12日)
- 【ライブ】『大雪ニュース』 “クリスマス寒波”襲来 / 猛吹雪による交通障害などに警戒を/ 高知で観測開始以来1位、徳島でも39年ぶりの大雪 など(日テレNEWS LIVE)
- 【速報】岩手県で記録的短時間大雨情報(2022年6月11日)
- 「泣きながらお母さんに『ごめんなさい』と言っていた」 “孫悟飯”に脅され強盗の実行役 “予行練習”から出頭までの一部始終が明らかに|TBS NEWS DIG
- 佳子さまがお召しに?「同じものが欲しい!」ブルゾンが大人気で完売!|TBS NEWS DIG #shorts
注目はNATO首脳会議「行き過ぎた支援は生物兵器使用を誘発」専門家解説(2022年3月23日)
停戦の出口が見えないなか、NATO・G7はどう立ち向かうのでしょうか。ロシア情勢に詳しい防衛省防衛研究所の兵頭慎治さんに聞きます。
(Q.数千人程度のベラルーシ軍がウクライナ侵攻に加わる可能性があるという報道がありますが、実際に参戦することはあり得るのでしょうか)
これまでルカシェンコ大統領は、参戦には慎重な姿勢を見せてきました。ただ、ロシアとの力関係では弱いので、プーチン大統領から派兵を求められているなかで、派兵せざるを得ないという可能性はあると思います。ベラルーシ軍は、約5万人弱しかいませんので、数千人程度だとかなり小規模な派兵にとどまります。
仮にベラルーシが参戦しても、ロシア側の反転攻勢にはならない。現在、ロシア側は手詰まり感を感じているなかで、何とかベラルーシ側からの支援を得たいと考えていると思います。一方、ベラルーシとしては、小規模でも参戦してしまうと、ロシアと共犯ということになりますので、欧米諸国から厳しい経済制裁、相当な代償を負うことになると思います。
今後の外交日程ですが、24日にNATO首脳会議が開かれ、ウクライナのゼレンスキー大統領がオンライン演説する予定です。また、その後に行われるG7首脳会議では、岸田総理が出席します。25日にはアメリカのバイデン大統領がポーランドを訪問します。
(Q.どこに注目しますか)
NATO首脳会議。アメリカとヨーロッパの国々が、どういう話し合いをするのか注目しています。会議の中で、恐らくウクライナへの派兵も含めた軍事支援をやるべきだという声が一部で上がってくるのではないか。ただ、バイデン大統領は派兵に関しては慎重な姿勢を崩していませんので、両者がどう折り合って、足並みをそろえていくのかが注目されます。そのあと、バイデン大統領はポーランドを訪問し、首脳会談を行います。その狙いは、国境付近に攻撃が及びつつあるので、ポーランドに寄り添う姿勢を示しながら不安を解消。また、多数の避難民を受け入れていますので、労をねぎらうというところもあると思います。もう一つ、ポーランドの首脳が、かつて、キエフに平和維持部隊として派兵すべきと意見を述べたことがあります。これはロシア側を刺激する可能性がありますので、こうした動きを少し抑えるという狙いもあると思います。
(Q.アメリカが直接的な軍事支援に踏み切ると可能性はありますか)
派兵など直接的な軍事介入は、難しいのではないかと思います。ロシア側は、それをけん制するために、化学兵器や生物兵器、その先には核兵器の使用もあると示唆しています。なおさら、アメリカは、直接的支援・介入に関しては慎重にならざるを得ない。あまり行き過ぎた軍事支援をやってしまうと、逆に生物・化学兵器の使用を誘発してしまう可能性があるので、そのあたりをどうNATOの首脳間で調整していくのかが焦点となります。
(Q.NATOやG7の首脳会議が、どう停戦につながっていくのでしょうか)
欧米諸国が行っているのは、武器や資金の軍事支援と経済制裁。これによって、中期的なロシアの行動を抑止していこうというところがあります。ただ、短期的な停戦となると、こうした支援だけでは難しいので、当事者間でやっている停戦協議。ここで一刻も早く、事態打開の糸口を見つけて、停戦にこぎつけてもらいたいと思います。
(Q.ゼレンスキー大統領の演説に出てきた“復興”という言葉。ゼレンスキー大統領の意思はどこにあると思いますか)
日本に向けたキーワード『津波』『原発』『復興』と出てきました。戦争はいずれ終わり、そのあと、復興が始まります。日本が経験した復興の経験と教訓。何をウクライナに伝えていけるのか。これは、日本ならではの支援になると思います。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>






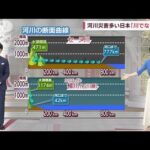











コメントを書く