- 【速報】新型コロナ新規感染 東京6264人、全国6万6397人 厚労省(2022年11月6日)
- 『同性婚は議論の過程にある…』大阪地裁は“同性カップル”の訴え棄却…「合憲」判断(2022年6月20日)
- 【ライブ】速報:異次元緩和を継続へ 日銀・黒田総裁を振り返る――日本銀行新体制へ 総裁として最後の会見 / 物価上昇2%目標掲げる / 日銀の役割とは・・・ など(日テレNEWS LIVE)
- 【ラーメンライブ】「ラーメン多めに」 こだわり店主の東京ラーメン物語 /“お値段据え置きの店”は今… など “every.グルメ”シリーズ一挙公開 (日テレNEWS LIVE)
- 知床観光船行方不明 船長 去年も同じ船で座礁事故|TBS NEWS DIG
- 【義母殺害容疑】茨城家庭内殺人 別の刃物見つかる
命をつないだ「防災食」 福島“復興”に向けた原動力に
災害によりライフラインが途絶えた時、最も重要なものは「水」と「食べ物」です。この、命をつなぐ「防災食」の開発に、東日本大震災で過酷な経験をした福島県も、果敢に挑戦しています。
今すぐにでも口に運びたくなる、新鮮な“シャモ”。実は、長期保存が可能な防災食です。
先月行われた、防災食品の展示会。東日本大震災が起こる前はおよそ100団体でしたが、現在は200前後の団体が参加していると言います。
2011年、その市場規模は128億円でしたが去年はおよそ230億円と10年間で2倍近くにまで拡大。日本ハムや永谷園など大手企業も続々と参入するこの市場に、果敢に挑戦する地方の食品事業者がいます。
川俣町農業振興公社 渡辺良一代表取締役
「福島は震災でいろんな思いがありましたので、『食べるんだったら美味しいものを食べたい』と」
南海トラフ地震が起きた場合、高さ16mもの津波が来ることが想定されている、高知市。
来たる大災害に備え、様々な防災対策を講じていますが、中でも力を入れているのが「防災食」の開発です。安全性などの基準を満たした「防災食」を県が認定し、官民一体となって積極的に売り出しています。
そのひとつが、豆腐のジャーキーです。薄く切った豆腐を乾燥させ、燻製にすることで、5年間もの長期保存が可能となっています。
株式会社タナカショク 田中幸彦社長
「炭水化物を取り続けると、体に変調をきたしたというデータが(ある)。(栄養の)バランスを崩さないための補助食として活用していただけたらなと」
高知県は、単なる「防災対策」にとどまらず、それを「地元産業の成長」につなげる取り組みを全国の自治体に先駆けて行ってきました。
株式会社タナカショク 田中幸彦社長
「『どうせまた大手さんが作るだろう』ではなくて、まずは(防災製品について)考えてみること、名乗りを上げてみること、そこが一番重要じゃないかと思います」
川俣町農業振興公社 渡辺良一代表取締役
「びっくりしましたよ。最初ドーンと来て横揺れもあって」
福島県川俣町で食品会社を経営する渡辺良一さん。大震災当時も、この工場で働いていたと言います。
当時、町には、福島第一原発のある海岸沿いの街から、大勢の人が避難してきました。
川俣町農業振興公社 渡辺良一代表取締役
「やっぱり震災後すぐは、いろんな方が(避難に)来ていたので、そういう方々はいろいろ食べ物に困ったと思います」
ライフラインが途絶えてしまう災害時に、人の命をつなぐの「水」と「食料」です。震災後、わずかな備蓄しかない過酷な状況を経験した渡辺さんは、改めて“食の重要性”に気づかされたといいます。
高知県に続けと言わんばかりに、昨年度から福島県も、地元の食材を使った防災食を開発する食品事業者をサポートする取り組みが始まりました。出来上がった商品は、各地で展示会を開き、積極的に福島の“防災食”を売り出しています。
客
「常備食ってまずいイメージが今まであったんですけど、まさかこんなご飯とアヒージョがあると思ってなかったので」
渡辺さん達が推奨しているのは、“普段から食べ慣れているもの”を家庭に備蓄することです。そして、防災食が身近な存在になってほしいと言います。
農業振興公社 渡辺良一代表取締役
「(災害時は)今までの生活と変わるわけですから、ストレスとかそういうものが一番大きいと思う。ほっとするっていうんですかね。美味しいもの食べて、もうちょっと頑張れるなとか、そういう思いになっていただければ良いですね」
震災当時、被災地で命をつないだ“防災食”。今は、“復興”にむけた一つの原動力になっています。
(08日12:37)





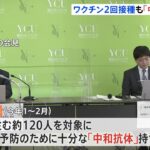






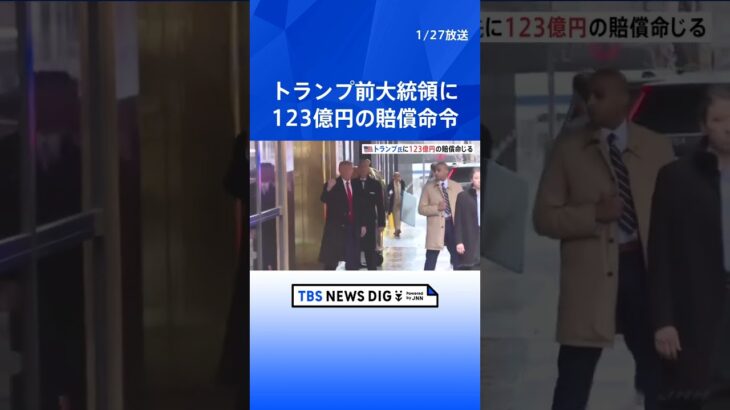
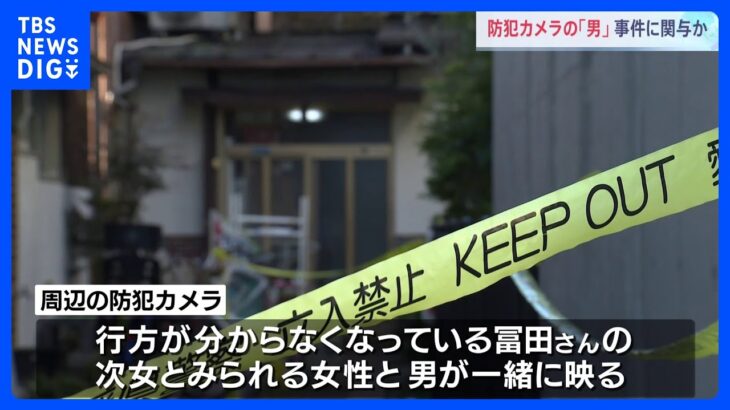


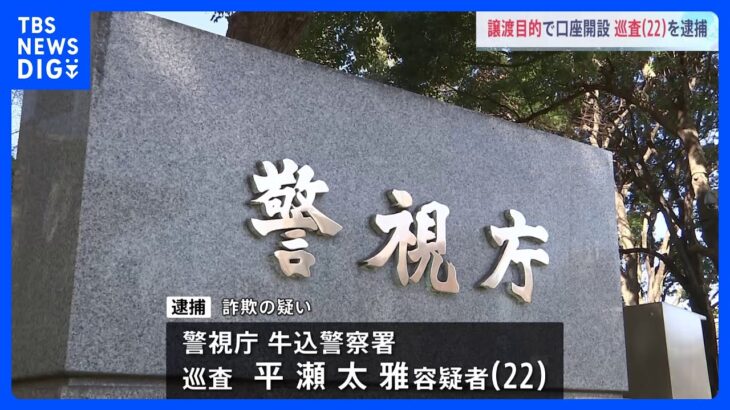

コメントを書く