海中に沈んだ「駅」 100年前の震災から学ぶ「土砂災害」のリスク|TBS NEWS DIG
関東大震災の教訓を未来につなぐ「つなぐつ、ながるプロジェクト」です。100年前の震災では、激しい揺れで多くの土砂災害が発生しました。その痕跡をとどめている場所が海の中にあります。
関東大震災から100年を迎えた1日。神奈川県小田原市根府川で、犠牲者を追悼するために手を合わせていたのは“ダイバー”です。
考古学者 林原利明さ大ん
「今から100年前、関東大地震によって引き起こされた地すべり。震災による痕跡が残っている」
100年前、ここで何が起きたのか?水深10メートルの海底で見えてきたのは…
「2本の棒のようなものが並ぶ。磁石を近づけてみると、しっかりとくっつく」
磁石がつく金属の棒、鉄道の「レール」である可能性があると言います。
さらに…
「同じ大きさの石が横にきれいに並んでいる」
等間隔に石が積まれているのは、駅の「ホーム」とみられています。なぜこうしたものが海の中で見られるのでしょうか。
現場は、JR東海道線根府川駅の沖、およそ300メートル。100年前の震災では、標高50メートルに位置する駅と列車が海に崩れ落ち、およそ130人が犠牲になりました。
「震災当時のものがそのまま残っていますので、防災意識とか減災意識を高める形では、非常に重要なもの、一つのツール」
根府川駅は、地震の揺れで地下水を含んだ地層がすべり面となり、海に向かって崩れ落ちたと見られています。この土砂災害を調査した京都大学の釜井名誉教授。全国的にこの100年で土砂災害のリスクが高まっていると指摘します。
京都大学 釜井俊孝名誉教授
「われれわは100年間の間に谷を埋めたりして、平らな土地を都市の郊外にいっぱい作ってきた。そういったものは一部は、地震の場合には崩れる可能性がある」
山を削り、谷を埋めた盛土造成地でも地下水が溜まると、地震の揺れをきっかけに崩れ落ちる危険性があります。実際、阪神・淡路大震災や北海道の胆振東部地震など、大きな地震のたびに盛土で被害が発生しています。戦後、宅地開発が進んだ地域に多い大規模盛土造成地。全国で5万か所を超えています。
京都大学 釜井俊孝名誉教授
「盛土かどうかということはそれだけで一つのリスクの要因なので、それを洗い出していただいて、亀裂があるかどうか、地下水がどうか、調べていただくことが大事」
▼TBS NEWS DIG 公式サイト https://ift.tt/5b6nptx
▼チャンネル登録をお願いします!
http://www.youtube.com/channel/UC6AG81pAkf6Lbi_1VC5NmPA?sub_confirmation=1
▼情報提供はこちらから「TBSインサイダーズ」
https://ift.tt/8g6s5tn
▼映像提供はこちらから「TBSスクープ投稿」
https://ift.tt/SGcwyEt












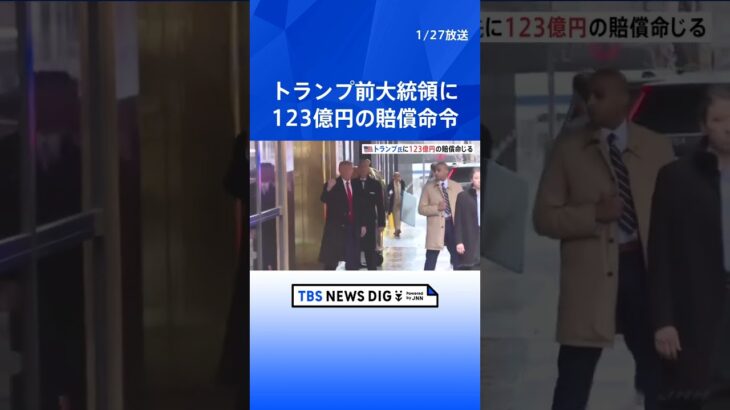
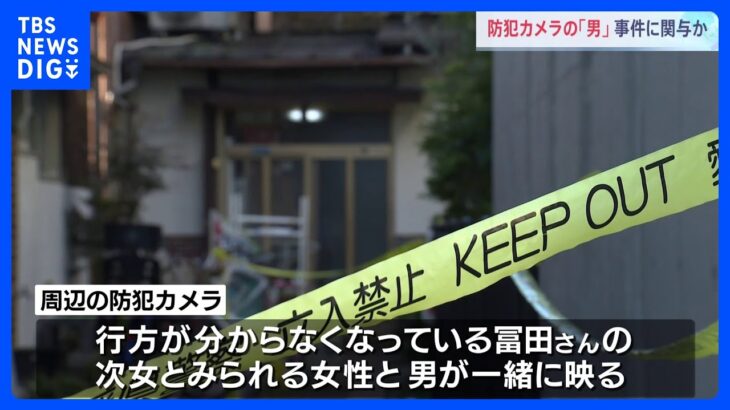


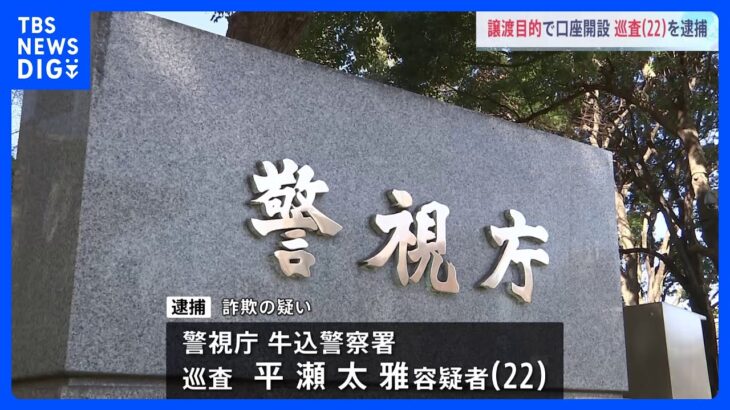

コメントを書く