「人生が一変」300万人超が避難・・・大越キャスターが見た“支援の最前線”(2022年3月16日)
ウクライナから国外に避難した人の数は300万人を超えました。
100人以上の職員がウクライナ国内で活動する難民支援の最前線、UNHCR=国連難民高等弁務官事務所の広報官も驚きを口にします。
UNHCRのマシュー・ソルトマーシュ広報官:「短期間にこれほどの避難者が出るとは、誰も予想できなかったでしょう。推定では400万人に達するとみられているが、さらに増える可能性が高いというのが国際社会での認識。現在、懸念されるのは、リビウを中心とする西部の数百万人に戦火が迫ってくれば、その多くが避難することになるでしょう。戦争の被害を受けたり、避難を余儀なくされれば、人生が変わってしまう」
長期化が見込まれるなか、支援の現場では、すでに課題が浮き彫りになっています。
ポーランド国境の街・メディカ。スポーツセンターだった避難所は、これまでに延べ2000人が身を寄せてきました。食堂に家庭の味が並び、避難してきた人たちが、束の間の憩いの時を過ごせるのも、ボランティアの力添えあってこそです。
ボランティア・プシビルカさん(35):「600キロ先の街から来た。ここで助けが必要だと知って、友だち2人と1週間の予定で来た。仕事は休暇を取ってきた」
ただ、こうした支援がいつまで続けられるのか。市長は、不安を口にします。
メディカ・イバシェチュコ市長:「ここは定員240人だが、600人以上が一夜を明かしたこともある。戦争が長引けば1つの国、県、郡では対応できない。できるときまで、できる限りのことをやり続けるだけ」
避難する人の変化も影響を及ぼしつつあります。ソルトマーシュ氏は、避難する人たちに“変化”がみられるといいます。
UNHCRのマシュー・ソルトマーシュ広報官:「当初は、すぐに国外に避難できる手段や資金があって、ポーランドなどに友人や親戚がいる人ばかりだった。ただ、そういった人は少なくなった。この数日間、ポーランドでは避難者数は、横ばいか少し減少しているものの心に傷を負った人が多くなっている。戦闘を間近で見て、心に傷を負ってしまったのでしょう。しかも、多くの人は危険ななかを何日も移動するが行く当てもない」
今後は、長期的な支援も課題となってきます。
UNHCRのマシュー・ソルトマーシュ広報官:「(Q.避難者が長期的に国外で暮らすために必要なものは)“都市型難民対策”でしょう。ウクライナから避難した人を社会に迎え入れるモデル。定住先となる国が避難者に行政サービスを提供する。教育、医療、雇用機会、住宅支援など。これが我々にとって理想のモデルであり、最善の対応。生活を安定させることができる。そうすればやがて労働や納税という形で社会や地元の経済にも還元することになる。我々としては、最善の難民対応として奨励している。必要とされる場所なら、どこへでも行く。最後までやり抜くが信念」
◆大越健介キャスターの報告です。
(Q.大勢の避難民がポーランドに入っていますが、受け入れの限界にきているというのは実感しますか)
実感します。取材した国境の街・メディカのシェルターは、バスケットボールのコート3面くらいある広さの体育館ですが、そこに隙間もないほど、簡易ベッドが並べられていました。その様子を一目見ただけで、もう限界に近づいていると感じました。
一方で、ボランティアの皆さんは献身的に働いています。3人の高校生に出会いました。この高校生たちは、学校に休みを申請し、150キロ離れた街からバスで来て、子どもの遊び相手をしていました。12時間働いて、夜のバスで帰るということでした。ただ、こうした非常時の支援体制も、どこまで永続的なものか。どうしても疑問を持たざるを得ません。国際社会が協力して、組織的な支援体制を組む、スキームを組むということが急務だと感じました。
(Q.ウクライナに支援物資を送るということに支障が出てきているのでしょうか)
そのことが最大の懸念になってきています。ウクライナから逃れてきた避難民に対する支援と並んで、ウクライナ国内にとどまって苦しんでいる人たちへの支援をどう構築していくのか、非常に差し迫った課題になっています。私がいる倉庫には、さまざまな物資、食糧などが集積されています。ここからトラックで運ばれて、ウクライナ西部のリビウなどに運ばれ、そこで荷物を積みかえて、さまざまな町に運ばれていきます。しかし、報じられているように、いくつかの街は、ロシアに制圧されています。首都キエフもロシアが包囲網を築きつつあります。このため、輸送は困難で、極めて危険を伴う作業です。こうした物資が滞れば、それは、苦しんでいる人たちの命の危険へとつながります。UNHCRの高官も「そこが悩ましい」と話していました。
一刻も早く停戦をすることが望ましいですが、この現場で話を聞きますと、喫緊の課題は、輸送物資を運ぶトラックのドライバーが不足していることです。その人手を確保したいということです。そして、UNHCRの高官は、もう一つ、とても大切なことを話していました。「世界中からのウクライナへの支援は感謝している。日本から取材に来たことについても感謝している。それと同時に忘れてほしくないことがある。それは、こうした人道危機というのはウクライナにとどまらず、中東やアフリカなどで、今も現在進行形で起きていることを忘れないでほしい」と話していました。そのためにも必要なのは資金です。私たちひとりひとりに対して善意を形にしてほしいと話していました。そのことが強く印象に残りました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>





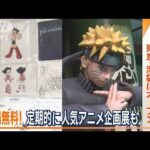












コメントを書く