【関東大震災100年】「“すべる地層”関東一円に」専門家 土砂災害が作った湖から警告(2023年8月31日)
シリーズでお伝えしている「関東大震災100年の教訓」、今回のテーマは地震による「地すべり」です。地質学者は「滑りやすい地層は関東一円に広がっている」と警鐘を鳴らしています。
深田地質研究所 千木良雅弘理事長:「あそこに白い地層が見えますが、あれが『(東京)軽石層』これと同じ地層に“すべり面”ができて、上のほうが『地すべり』を起こした。(『軽石層』の土を)練ると泥水のようになる。“泥水”の上に地層は乗っていられず『地すべり』してしまう」
神奈川県秦野市の「震生湖」は、関東大震災による地すべりで川がせき止められてできました。
周辺でも地すべりが相次ぎ、行方が分からないままの子どももいたそうです。
神奈川県では西部を中心にこうした土砂災害が相次ぎました。
気象庁が今年、初めて公開した記録写真の中にある土石流の写真からは、瓦葺(ぶ)きの家々を土砂や木々が覆うように流れてきた様子が分かります。
手前の家は土壁が崩れているようにも見えます。
また、東海道線の根府川駅に直撃し、130人の犠牲者が出た土石流の被害の写真も残されています。
海岸に落ちた列車の一部や、駅に近い大きな橋が土砂により横に倒された様子が分かります。
これらの土砂災害について、非常に強い揺れに加えて前日に降った雨も原因だとされますが、詳しいメカニズムが分かっていないものもあります。
このうち震生湖については発生した詳しいメカニズムが分かってきました。
京都大学の研究者だった千木良雅弘さんは7年前に、地下に広がる“東京軽石層”という地層が風化して崩れて起きたと突き止めたのです。
千木良雅弘氏:「(『東京軽石層』は)箱根山から噴出し神奈川から東京に広く分布。軽石は大雨ではあまり崩れない。地震で崩れることがある。特に『軽石層』がある斜面の下の方が工事などでなくなると『地すべり』しやすい。(住宅地で発生なら)上に乗った家は一緒に滑るし、下の方では横から来た土砂ですごい被害に…」
東京軽石層は7万年近く前の箱根山の火山活動でできたものです。
軽石層は各地の火山活動によって全国的に広がっていて、2018年の北海道胆振東部地震の地すべりも、軽石層が崩れたことによるものでした。
また、現在の行政の課題として、斜面の危険度を示すハザードマップで、大雨は考慮されていても、軽石層のリスクは見落とされていることを指摘しています。
千木良雅弘氏:「(Q.個人で調べられる?)個人では限界がある。ハザードマップに、こういう“ゆるい傾斜”での地震時の『地すべり』は入っていない。(行政機関中心に)なんらかの対策や被害の評価をしていかなければ。地震時の軽石などの『地すべり』はそんなには起こらないので“網の目から漏れた状態”なのでは」
千木良さんによりますと、軽石層の崩れる速さは場合によっては時速100キロと逃げられないほどの速さになるため、リスクがある地域の家に住む人たちができる対策は寝る場所を2階より上にすることくらいだとしています。
そのため「街中に軽石層が隠れている恐れが高く、国レベルで状況を把握して周知していくべきだ」とも訴えています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
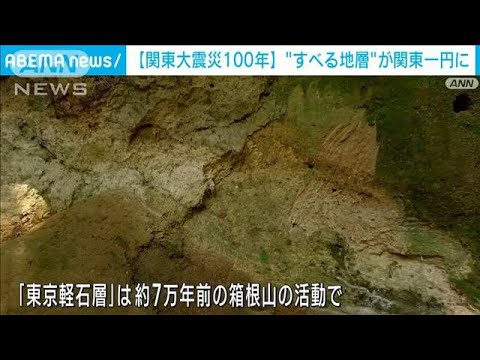



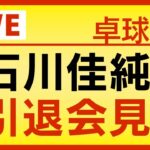













コメントを書く