- 【天気ライブ】上野公園 ライブカメラ 桜雨・花冷えーーCherry blossoms at Shinobazu pond in Ueno,Japan
- 待ちに待った!?“都民割”「もっとTokyo」が9月1日に再開へ 通常の半額以下で宿泊できるプランも登場|TBS NEWS DIG
- 青葉被告の控訴取り下げ 弁護人が「無効」を申し入れ 36人死亡の京アニ放火殺人 一審で死刑判決 #shorts #読売テレビニュース
- 林外務大臣 中国外交トップに日本人男性解放を要求(2023年4月3日)
- 【大興奮】大好きな雪に大はしゃぎ! 柴犬「ハル」ちゃんのダイブ(2022年12月22日)
- 米メーン州 18人死亡銃乱射事件 容疑者の男遺体で見つかる #shorts
時代小説作家・池波正太郎 “生誕100年”バスツアー開催…人気の理由「庶民的視点」(2023年3月18日)
「鬼平犯科帳」や「仕掛人・藤枝梅安」などの時代小説作家・池波正太郎さんが生誕100年を迎えた。出身地の東京・台東区では、池波さんのゆかりの地や作品に登場する場所を巡るツアーで盛り上がっている。
■“生誕の地”“作品にまつわる場所”巡る
時代小説の大家・池波さん。江戸の下町を舞台にした三大シリーズは小説のみならず、ドラマや映画、マンカなどでも有名だ。
「鬼平犯科帳」は、実在した火付盗賊改方・長谷川平蔵が主人公。平蔵が仲間とともに、凶悪化する江戸の犯罪を取り締まる捕物帳だ。
そして「仕掛人・藤枝梅安」は、人を助ける立場の鍼医者・梅安が、世の中に生かしておいては人のためにならない悪人殺しを請け負う。
池波さんは1923年1月、現在の東京・台東区浅草に誕生し、その後も主に東京の下町で暮らし続けた。
今年は、ちょうど生誕100周年にあたり、そのゆかりの地や作品に登場する場所を巡るツアーが開催され、人気だという。一体どんなツアーなのか。
一行が最初に向かったのは、池波さんの生誕の地だ。
観光ガイド:「1月25日、大変雪が降っている寒い日だったそうです。父親の富治郎は、朝から2階でお酒を飲んでいたら、お酒が切れてしまい、奥さんの鈴さんが身重の体をもって酒屋へ酒を買いに行きますと産気付いてしまい、そのまま酒とともにこの家に運ばれてきた」
ツアーでは、池波作品にまつわる、こんな場所もあります。
観光ガイド:「鬼平犯科帳に出てくる『嶋や』という船宿がこちらのほうにありました」
船宿「嶋や」は、「鬼平犯科帳」に度々登場する。現在は埋め立てられているが、江戸時代には、今戸橋という橋が架かっていた近くにあったと、作品では設定されている。
■昼食は…「鬼平犯科帳」に登場する“軍鶏鍋”
このツアーに同行するのが、1975年から亡くなるまでの15年間、池波さんのアシスタントを務めた、鶴松房治さん(75)。
現在は「池波正太郎記念文庫」の指導員として、時代小説作家にまつわるエピソードを語り継いでいる。
鶴松さん:「第1作を書くという時は、細かい筋立てとか構成・あらすじは一切考えずに、書き出しがひらめいたら、すぐに書く。あとは自然の筆の流れにまかせて書く。だから自分でも結末は分からない。つまり、培った感性みたいなものを一番大事にしていた。これは物を作る職人さんと同じ感覚だと。だから自分は“作家という職人”なんだ、ということをいつも言っていました」
また、“食通”としても知られ、食にまつわるエッセーを数多く出版してきた。
鶴松さん:「小説の中に食べ物を出すというのは、これは『季節感』を出したかったから。それで、結構食べ物を書くようになったようなんですね」
バスツアーでは、池波作品に登場する「味」を堪能できることも、目玉の一つだ。
昼食では、「鬼平犯科帳」に度々登場する「味」が楽しめる。小説で、主人公・平蔵がなじみにしていた架空の店が、「軍鶏(しゃも)なべ屋・五鉄」。そこで出されていた軍鶏鍋を再現した。
新鮮な軍鶏肉と臓物を、初夏のころから出回る新ゴボウのささがきと一緒に、だしで煮ながら食べる。「夏の快味であった」と小説には書かれている。
江戸料理「櫻田」 店主・櫻田勝彦さん(78):「(江戸時代に)しょうゆというのは下り物といいまして、和歌山のほうからしょうゆが来ていたので高かった。だから、味噌仕立てのほうが多かったのでは」
ツアー参加者:「こんなぜいたくな、昔の人が食べたのなら、おいしいって言うよね」「やっぱり肝が入っていると、コクが出ておいしいですね、肉だけじゃないので」
この店では、土日の昼間だけ、この軍鶏鍋が食べられるという。
■江戸風情と味を楽しみ…参加者「近年にない楽しさ」
小説の主人公らと同じく、池波さん自身も古くから受け継がれる、江戸の味を好んだという。
隅田川に面した駒形の地で、およそ220年の歴史を誇る、うなぎの老舗「前川」には度々、足を運んだそうだ。
駒形前川 七代目・大橋一仁さん(44):「もともと幼少期、おじいさまに連れてきていただいて。その晩年、色々と物書きで静かに自分の時間を作る時には、弊社のほうに来ていただいて、お酒を飲みながら時間を作って。そして、かば焼きを召し上がってという話は聞いております」
かば焼きが出されるまでの時間、お新香などをつまみに、酒を飲みながら、江戸風情を楽しんでいたとされる。
池波さんが描いた江戸の風情と味を楽しんだツアー客に話を聞いた。
ツアー参加者(80代):「40代のころ読みあさっていたので、夫と2人で。忘れた部分が多いけど、お話しされると思い出す。もう近年にない楽しさ」
ツアー参加者(60代):「江戸時代の、そういう世界というのはできたら行ってみたいと思いました」
■小説家としての土台は“10代の社会経験”
今も池波さんの作品が人気のワケについてみていく。
池波さんは1923年(大正12年)の1月25日に、当時の東京市浅草区で生まれた。
その8カ月後、関東大震災が起き、一家は当時の埼玉県浦和市に疎開するが、6歳のころに再び浅草に戻ってくる。
そして小学校を卒業すると、池波さんは12歳から株式仲買店に務めた。
戦後の1948年、25歳の時に“大衆文学の父”とも言われる劇作家の長谷川伸さんの門をたたき、脚本を書いて生きていくと決心したそうだ。
その後、脚本家・小説家として数多くの作品を生み出した。
池波さんのアシスタントを15年間務めた鶴松さんは、12歳で社会に出てからの経験が小説家としての土台になっているといい、「株式仲買店には色んな人が出入りするので、10代のうちから大人の世界に足を踏み入れ、人生経験を積んだことが作家としての土台になっている」と話す。
■人気絶えず…池波文学の大きな特徴“庶民的視点”
池波作品は江戸を舞台にした作品が多くあるが、その理由を鶴松さんは、「まだ江戸の名残が色濃く残る町で幼少期を過ごした池波は、江戸の名残を肌で感じて育った最後の世代だと思う。なによりも『町が好きな作家』であり、池波が最も好きな、いつまでも住んでいたい町として江戸を書いたのだと思う」ということだ。
「鬼平犯科帳」で言えば、連載がスタートしてから50年以上経っているが、今でも池波作品の人気が絶えないことについては「鬼平犯科帳だと長谷川平蔵が理想的なリーダーとして描かれていることや管理職である平蔵の人心掌握術など、今の時代の人が納得でき、参考になる内容になっている。また下町育ちの人々を代表するような庶民的な視点で作品を構築している。それが池波文学の大きな特徴で皆さんが楽しめる要素ではないか」と話した。
(「大下容子ワイド!スクランブル」2023年3月17日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
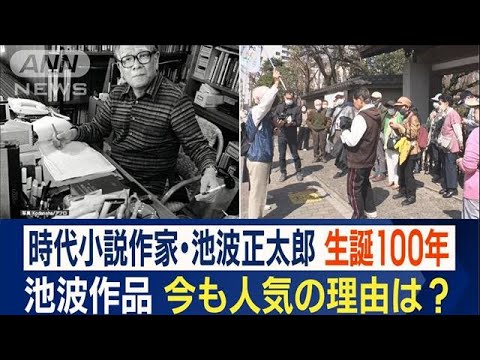









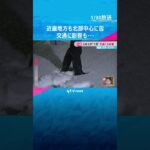







コメントを書く