月で“謎の発光”観測に成功…各地で“火球”関係は?(2023年3月1日)
事故処理中でしょうか、片側を規制された道路。警察車両の横を通り過ぎたその時。上空に見えたのは火球でした。しかも、5秒ほどの長い時間。
先月28日夜8時ごろ、関東などの広い範囲で火球が観測されました。福島県で撮影されたものは青白い色まではっきり分かります。先ほどの火球とは、別のものが九州でも観測。特に流星群の時期でもないですが…。
平塚市博物館・藤井大地学芸員:「『流星群』は、すい星から放たれたちりがある時期にまとめて群れをなして、流れ星になる現象を『流星群』といいます。『散在流星』はですね、宇宙を漂うちりがたまたま地球とぶつかって流れ星になる」
今回の火球は、この「散在流星」だそうです。
実は、藤井さんが23日に撮影したある映像が話題になっています。月に向けたカメラの映像ですが、誰も人が住んでいないはずの月面から一瞬、光が。誰が何のために。今、月面で何が起こっているのでしょうか。
平塚市博物館の天文担当学芸員・藤井さんが撮影に成功した誰もいないはずの月面の発光現象。この映像は一体…。
平塚市博物館・藤井大地学芸員:「大気のない月では『流星現象』というのは起きない。そのまま、ちりや小石が月面に衝突して、その衝撃によってクレーターができるんですけど、クレーターができる瞬間に光る現象があって、これを『月面衝突閃光』と呼ぶんです」
つまり、これは偶然にも月面に「微小天体」が衝突した瞬間の映像です。観測できる時間帯も限られ、撮影できるのは「月の夜」の部分のみ。この映像も衝突位置がもう少し右側であれば、観測も撮影もできなかったところでした。
明るさや大きさ、発光時間の長さから考えても、かなり珍しい映像だそうですが、なぜ衝突した瞬間に発光するのでしょうか。
平塚市博物館・藤井大地学芸員:「宇宙から降ってきた石が月面にぶつかると数千℃という高温になります。非常に熱い物体からは『光』が出ますので、その光が地球に届いて『衝突閃光』として見えている」
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>




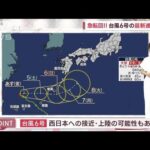













コメントを書く