「ナルトビエイ」受精卵9カ月半も休眠 成長過程で新発見(2022年1月31日)
「ナルトビエイ」というエイの一種が、受精卵を9カ月半も休眠させることが分かったと、長崎大学の研究グループが発表しました。
長崎大学の山口敦子教授によりますと、「ナルトビエイ」の子宮内で受精卵から赤ちゃんがどのように形作られるのか、世界で初めて詳細に記録することに成功しました。
その結果、夏に交尾・妊娠した後、受精卵は子宮内で分裂を始めるとすぐに休止して、母親の胎内にいる12カ月のうち、およそ9カ月半は休眠することが分かりました。
休眠から目覚めるとおよそ2カ月半で急速に成長し、翌年の夏に生まれてくるということです。
これにより、赤ちゃんが生き延びるのに最適な環境となる夏に出産を遅らせることが可能となっています。
また、母親の雌としては、夏に妊娠したとしても、休眠させることでおなかの赤ちゃんを育てるために必要なエネルギーを最小限に抑えて、冬を乗り越えることができます。
雌に比べて体が小さく死亡率が2倍ほど高い雄にとっては、死亡のリスクが高まる冬の前に交尾を済ませることができるということです。
山口教授は「厳しい環境下で生き残るための優れた生存戦略で、親と子の両方に利益をもたらすことが明らかになった」と話しています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>










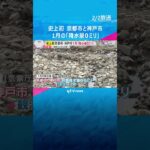







コメントを書く