「再生二期作」に挑戦 1つの株で1年に2度収穫、収穫量を増やす コメ不足の切り札に?滋賀・甲賀市
今年の新米の収穫量が気になりますが、その収穫量を増やすための新しいコメ作りがあるそうです。挑戦が進んでいる現場から中継です。
(取材・報告=切通大雅 記者)
滋賀県甲賀市から中継でお伝えします。こちらでは約20ヘクタールの田んぼが広がっていて、まさにこの時期、稲刈りが行われている真っ最中です。
私が今いるのは、刈り取りが行われたばかりの田んぼです。
稲刈りというと、いま刈り取ってしまうと、次は”来年”というのが一般的かと思いますが、こちらの農家では、刈り取った稲から再び稲を育てるということをされようとしています。
その方法、どのように行うかというと、そのヒントが、刈り取った稲の高さにあります。
だいたい10センチほどですが、新しい方法では、ここからちょっと伸ばして、40センチから50センチほどで刈り取ります。
さらに、ここに水を入れて再び水田にすると言うんです。その方法を実際に行った田んぼが、この横にあります。ご覧ください。
このように少しずつ稲ができてきて、実際に見てみると、穂が少しずつ実っているんです。少しずつできているのがわかるかと思います。
そして根元の方から40センチから50センチほどの高さを見てみると、刈り取られた跡があるんです。
このような農法を「再生二期作」と言います。一つの株で一年に二度の収穫をして、通常よりも多くの米を収穫しようとしているということす。
厳しい残暑が続くことを逆手にとった農法だということです。
ここからは、再生二期作を進める農家の山本さんに話を伺います。
黒木千晶キャスター
Q:1度目の収穫が進んでいるということですけれども、今年の収穫量や出来はいかがでしょうか?
山本和宏さん
「平年作よりは、少し少なかったように思います」
Q:今年、なぜ再生二期作というのを始められたのか伺っていいですか?
「やはり米不足ということで、たくさんの米を何としてでも農家が提供する必要があると思いまして、少しでも多く採るようにと思って、再生二期作に挑戦しました」
Q:今年1回目もあまり多くなかったという話ですが、今回この再生二期作でどれくらいの収穫量を目指していらっしゃるんでしょうか?
「初めての試みなので、1回目の半分でもあれば合格という形で進めていきたいと思っています」
Q:2度目の収穫はいつぐらいを目指していらっしゃるんですか?
「これから大体2か月後ぐらいの10月末から11月にかけて収穫できると思います」
Q:実際にやってみて、再生二期作の課題というのは見えてきていますか?
「やはり、この刈り取りの高さを高く刈るには、やっぱり今までのコンバインではやっぱりダメなので、汎用コンバインといいまして、刈高を高くするような機械が必要になってくるということが一番の課題だと思います」
(黒木千晶 キャスター)
やっぱり新しい投資も必要になってくるんじゃないかという課題もあるということですね。
(高岡達之 解説委員)
Q:私が気になっていることを一つ書かせてください。かつては高知県なんかでも二期作をやっていたんですけれども、農家の方からご覧になって、二回作ると土地の力と言いますか、栄養の力と言いますか、そういうものが落ちる怖さというのはないんでしょうか?
山本和宏さん
「それはやはりあります。やはり土地自体が痩せるということはやっぱり懸念していることで一番あることで、この辺はやっぱり堆肥とかまたそういったものを入れて土を復活させるということで、これは今後の課題となると思います」
(黒木千晶 キャスター)
それはそれでやっぱり負担になるということですよね。
■「再生2期作」コメ増産の切り札に?
(黒木千晶 キャスター)
コメ不足が続いている中で、「再生二期作」という取り組み。高岡さんの話にもありましたが「土地が痩せるんじゃないか?」という心配もあるということですけれが、福岡県で実際に実験が行われていて、合計の収穫量は県平均の約2倍、そして2回とも味はコシヒカリ並だったということです。通常のニ期作に比べて、再生二期作は「植え直しが不要」というメリットあります。
ただ一方で、2回やるので「長期間の水が必要」だというデメリットもあるということです。
ただ地球温暖化によって、稲の生育可能期間が、やはり暖かいので長くなったことが活用できる要因だということで、関東から九州の幅広い地域で導入が進んでいるということです。
(高岡達之 解説委員)
私は高知県の話をしましたが、スタジオでは私が一番年長なので。私が小学生の時はもうこれやってるのは、”高知県”というのは教科書に載っていたんです。
ただやはり、いま黒木さんが説明してくれたように、気候の問題があったり、土地の栄養力の問題があったり、でもこれ今の地球温暖化もそうですが、技術も進んだんです。 肥料も進んだんです。だからやれるようになったということだと思うんですけれども、やはりそれなりの負担を農家におかけするということは、我々の何か公的なことも考えていかないといけないという話になるんだろうなと。
(黒木千晶 キャスター)
先ほどの滋賀のように、水辺が近くにあるところはこういったことができるということなんですが、できる土地、できない土地があると思いますけれども、それぞれの工夫と努力で、何とかこのコメの量を増やそうとしている農家の方の努力が続いています。
▼特集動画や深堀解説、最新ニュースを毎日配信 チャンネル登録はこちら
https://www.youtube.com/channel/UCv7_krlrre3GQi79d4guxHQ
▼読売テレビ報道局のSNS
TikTok https://ift.tt/TcU3snK
X(旧Twitter)https://twitter.com/news_ytv
▼かんさい情報ネットten.
Facebook https://ift.tt/zKUQtCp
Instagram https://ift.tt/bsRLmGv
X(旧Twitter)https://twitter.com/ytvnewsten
webサイト https://ift.tt/LCi2B8D
▼読売テレビニュース
https://ift.tt/dMNXElh
▼情報ライブ ミヤネ屋
https://ift.tt/6m7Djgq
▼ニュースジグザグ
X(旧Twitter)https://x.com/ytvzigzag
webサイト https://ift.tt/dQTxLsr
▼す・またん!
HP:https://ift.tt/fbAaejK
X(Twitter):@sumatanent
Tweets by sumatanent
Instagram:@sumatanentame
https://ift.tt/vaifWA3
TikTok:@sumatantiktok
https://ift.tt/7hLUs0W
▼情報提供はこちら「投稿ボックス」
https://ift.tt/Zb70n95






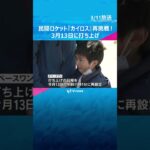




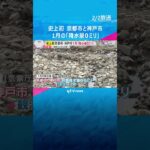
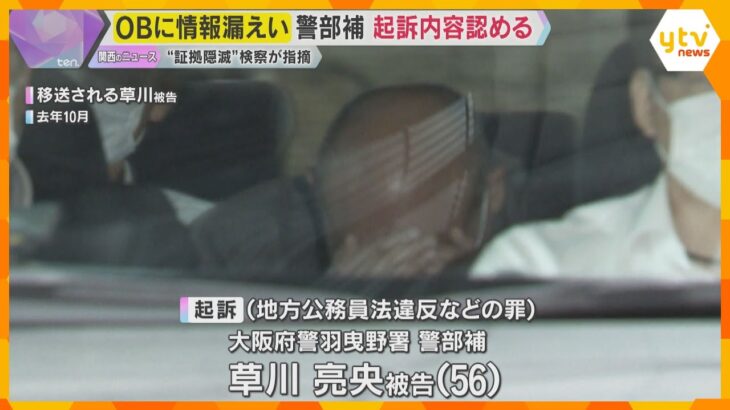

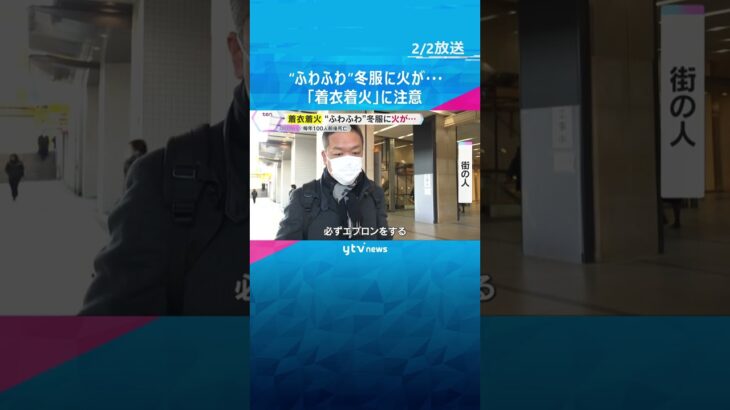
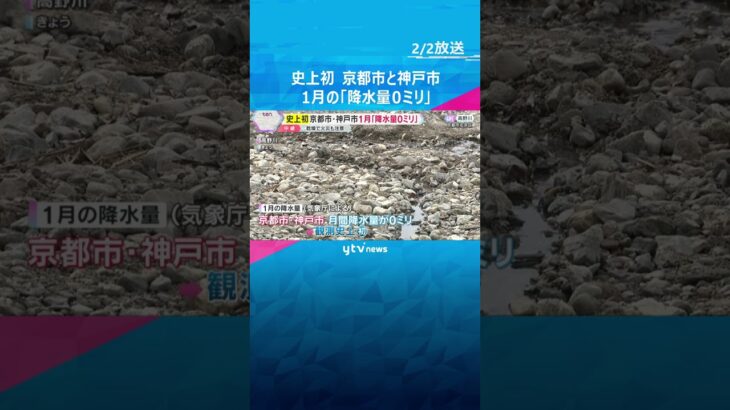
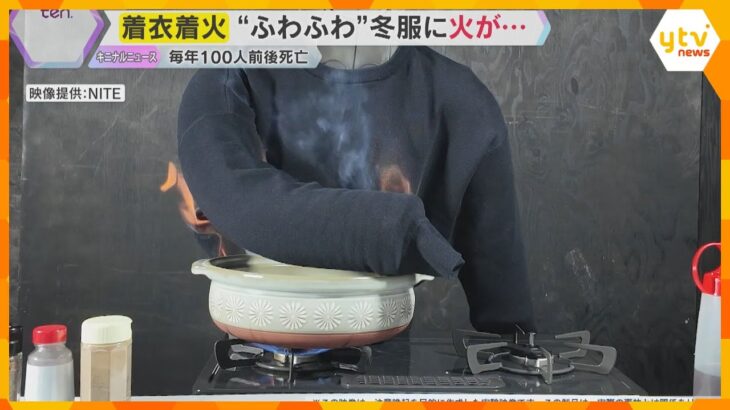

コメントを書く